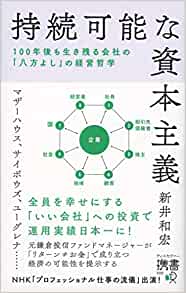目次
【起業おすすめ本】起業が成功する『持続可能な資本主義』
今回の起業東京.comでは、弊社の代表取締役である
元ドクターシーラボ社長「池本克之」おすすめの【起業おすすめ本】を紹介します。
ご紹介する本は、『本当にいい会社』とはについて考えています。
新井和弘著『持続可能な資本主義』
起業の勉強にどんな本を読むべきか悩まれているみなさん。
プロの経営コンサルタントであり、
現役代表取締役のおすすめする一冊、
手にとられてみてはいかがですか?
本書は、鎌倉投信株式会社取締役である新井和宏が、信頼と共感で成り立つ経済のしくみを考える一冊である。
本書には鎌倉投信株式会社の理念や理想が語られており、「これからの社会に必要とされる会社」、「経済性と社会性を両立している会社」など、いい会社(これからの社会に必要とされる会社)に投資するということを基本方針としている。
その理由は2つあり、ひとつはいい会社がお客様の信頼を獲得し、応援される時代になってきているため。
そしてもうひとつの理由は、社風や企業文化、社内外の信頼関係が築けているいい会社は、数値化できない見えざる資産を持っているためである。
著者は、この「いい会社」を増やさないことには資本主義が改善されることはないと述べており、多くの実在する企業の実例を交えつつ、投資する上で人的信頼づくりの大切さを繰り返し唱えている。
そして本書最大の目的は、そんな「いい会社」をこの世にひとつでも多く増やすことにあり、是非多くの投資家や経営者の方に読んでいただきたい一冊となっている。
「持続可能な資本主義」著:新井和宏
本書は下記の章で成り立っている。
- 人と社会を犠牲にする資本主義に永続性はない
- 効率至上主義の代案としての「新日本的経営」
- 現場を訪れてはじめてわかった、「いい会社」が大切にしていること
- 金融だから生み出せる信頼のレバレッジ
- 資本主義の未来は「個人」がつくる
この章では著者の経験を交えつつ、資本主義を改善するための必要条件を考える。
現在の経営方法は「リターン=お金」、つまりお金を稼ぐ事が投資のモノサシになっており、本来幸せを手に入れるための手段であったお金を増やすことが、いつしか自己目的化している。
かつて、著者は外資系運用会社時代で企業年金の運用を担当していた。当時、年金を管理する組織の担当部署の人間とは何度も顔合わせしていたが、その先にいる年金加入者の方々一人ひとりとは面識がなく、顔の見えない相手のために何百兆円の資産を運用していた。
そんな中、著書『日本でいちばん大切にしたい会社』(あさ出版2008年)に出会ったことで著者の「リターン=お金」の常識が根底から覆された。
その書籍には、社員の7割が障害社、社員を大切にする会社など、「いい会社」が数々紹介されており、これに感銘を受けた著者は鎌倉投信で「資産の形成×社会の形成×心の形成=幸せ」という新しいリターンの定義を掲げる。
これは、鎌倉投信のお客様が得るのはお金だけではなく、投資を通じていい会社の役に立つことで、受益者の心も豊かになるというものだ。
鎌倉投信はいい会社に投資しているが、いい会社を数値化するのは非常に難しい。
しかし、数値化してしまえば、企業は指標を満たそうとするあまり、個性を失う。定量化できないからこそ、現場に出向き、顔を突き合わせて話をすることが大切であると著者は語る。
「生」の情報が信頼の土台となり、ここから生まれた「信頼」は、数字から生まれただけの「期待」と違い、簡単には揺らがない。
これに基づき、鎌倉投信は直販にこだわり、銀行や証券会社の窓口を経由せずに直接お客様に販売している。
「三方よし」という言葉をご存知だろうか。
これは「売り手よし、買い手よし、世間よし」というスローガンのことで、商いは、売り手にとっても買い手にとってもプラスにならなければならず、世の中全体にも役立つものでなければならないという意味だ。
かつて銀行は数字にできないものを見て投資を行っていた。一軒一軒企業を訪問し、信頼関係を築いて融資していたのだ。ところが、1993年にIBS規制(1988年に国際的な銀行監督機関であるバーゼル委員会によって発表された、銀行の自己資本比率に関する国際基準)を導入したことによって、日本は社会的価値や人間的価値などの「見えざる資産」を評価する力を失ってしまったのだ。
IBS規制のほか、グローバリゼーションなどの影響を受け、日本は「三方よし」のアドバンテージを見失い、もともと体制が違うのにもかかわらず、アメリカの経営理論に縛られてしまった。
著者はこの打開策のヒントとして「CSV」を本書で紹介している。CSV(CreatingSharedValue)とは、ボランティアではなく本業で社会に貢献することを指すアメリカ発祥の考え方である。
CSVの考えを持っている企業かどうかは、ステークホルダー(利害関係社)との間に共通価値を見いだしているかどうかで決まる。CSVの詳しい解説は本書を手に取っていただいた後のお楽しみとしよう。
さて、ここで日本の「三方よし」と近年の「CSV」重視の動向をふまえて著者は新たな合言葉を提唱している。それが「八方よし」だ。
八方よしは、CVSの共通価値と三方よしの関わる者すべてが幸せになるという本質を取り入れたものである。
しかし、現代では三方では表せないほど経済が複雑化しているため、企業を中心として、「社員」「取引先・債権者」「株主」「顧客」「地域(住民・地方自治体など)」「社会(地球・環境など)」「国(政府・国際機関など)」「経営者」の八方に範囲を拡張する。
この八方よしの究極の形は八方に企業の「ファン」になってもらうことである。プロ野球を例に挙げて説明しよう。
プロ野球のファンはひいきのチームが勝つと喜び、負けると自分のことのように悲しむ。これは「優勝」という目標を共有してチームと同じ方向を向いているからだ。
しかしファンであり続けてもらうことはそう簡単なことではない。ファンはチームが試合のプロセスをしっかりと見ている。「今日の試合は勝ったけど、あんな戦い方をするのならファンをやめたいな」と思わせてしまう試合もあるだろう。
ビジネスでも同様、汚い戦い方をする企業にファンは生まれない。
ステークホルダーにファンになってもらう第一歩は顧客や社員、株主に経営理念に共感してもらうことなのだ。
この章では第2章で挙げた「八方よし」の八方が具体的に解説されている。
ここでは「社員」の解説の一部を紹介する。前にも述べたように、「お金=リターン」の価値観に捕われると社員は仕事にやりがいを見いだせない。
「社員よし」を実現している会社は、社員を「コストの発生源」としてではなく「付加価値の分配先」として位置づけている。
そして「社員よし」を実現させる為に何より重要なのは「信頼」である。
今回は「日本一、社員が幸せな会社」を掲げる未来工業の経営を見てみよう。未来工業には「ホウレンソウ」(報告・連絡・相談)を強制するようなシステムが全くない。
企業が管理や強制をするのは、社員を信頼していないからであり、それでは自分で考えて働く社員は育たないというのが未来工業の考え方だ。
また、社員が自ら考えてすぐに実践できるような環境を整えており、「やってみてダメなら、元に戻せばいい」という考え方が浸透しているので、社員は失敗を恐れる事なく、常に前向きでいられる。
このように、会社から「やりたいようにやれ」と仕事を任せてもらえることは、社員が楽しく働けるモチベーションになり、そんな会社であれば当然社員は会社のファンになる。「社員よし」の経営は、社員を信頼することから始まるのだ。
ここでは著者の金融に対する考え方が簡潔にまとめられている。
金融はよく「社会の血液」にたとえられる。血の巡りが悪くなると体調を崩してしまうように、お金の巡りが悪いと経済活動は滞ってしまう。
そして筆者は現在の「社会の血液」に人間的な関係が欠如していると述べる。前にも述べたように人間関係を創造し、信頼を築くことを著者はとても重視している。
お金ではなく、信頼のレバレッジをかけることで、信頼を拡大させていく役割を担うのが著者の考える金融のあるべき姿なのだ。
資本主義を考えるにあたって、「経済成長が持続可能かどうか」を考えていただきたい。
資本主義は経済成長が続くことを前提として設計されているが、はたしてその前提は正しいのであろうか。
そもそも経済成長を続けなければならない理由として挙げられる最大の理由は人口増加だろう。
増え続ける人口を養うためにはお金が必要だ。しかし日本は既に人口減少社会に突入しており、経済成長を続ける必要はないと著者は述べている。
著者は「経済成長=善」という考え方にも警鐘を鳴らしている。ここまででも指摘してきたように、お金や利益を追求して犠牲になるのは社員、顧客のような人間だけではなく、自然環境、資源、なども含まれ、このままでは国家や社会が危機に陥ってしまう。
しかし、日本は元々「利益だけを追求するのは品格に欠ける」という意識が人々の暮らしの中に根付いており、日本は資本主義を継続可能なものにするポテンシャルを秘めている国だ。
人口減少、格差拡大、ブラック企業、少子高齢化、資源の枯渇など、日本が抱える問題はまだまだ多いが、「八方よし」の企業が全国に点在しているのも事実だ。
そしてその八方よしのいい会社を顧客として、投資家として、地域住民として応援するのは私たち個人なのだ。
著者は最後に、本書を手に取り、いい会社を応援して資本主義の未来を支えようと思ってくれる人が一人でも増えたら著者として何よりの喜びだと語っている。
まとめ
本書は著者である新井和宏の経営理念が紹介された一冊である。
誰も犠牲にしない資本主義は私たち消費者がよく考え、いい企業を応援することで実現する。それが社会、国、に還元されて自分たちに還ってくる。
本書で紹介されている八方よしが実現される数々の企業の経営理念を見るだけで希望が湧いてくるような読後感であった。
私たちが目指すべき未来はどのようなものだろうか。
投資家や経営者に限らず、資本主義の未来を担う若者にも是非薦めたくなるような一冊だ。