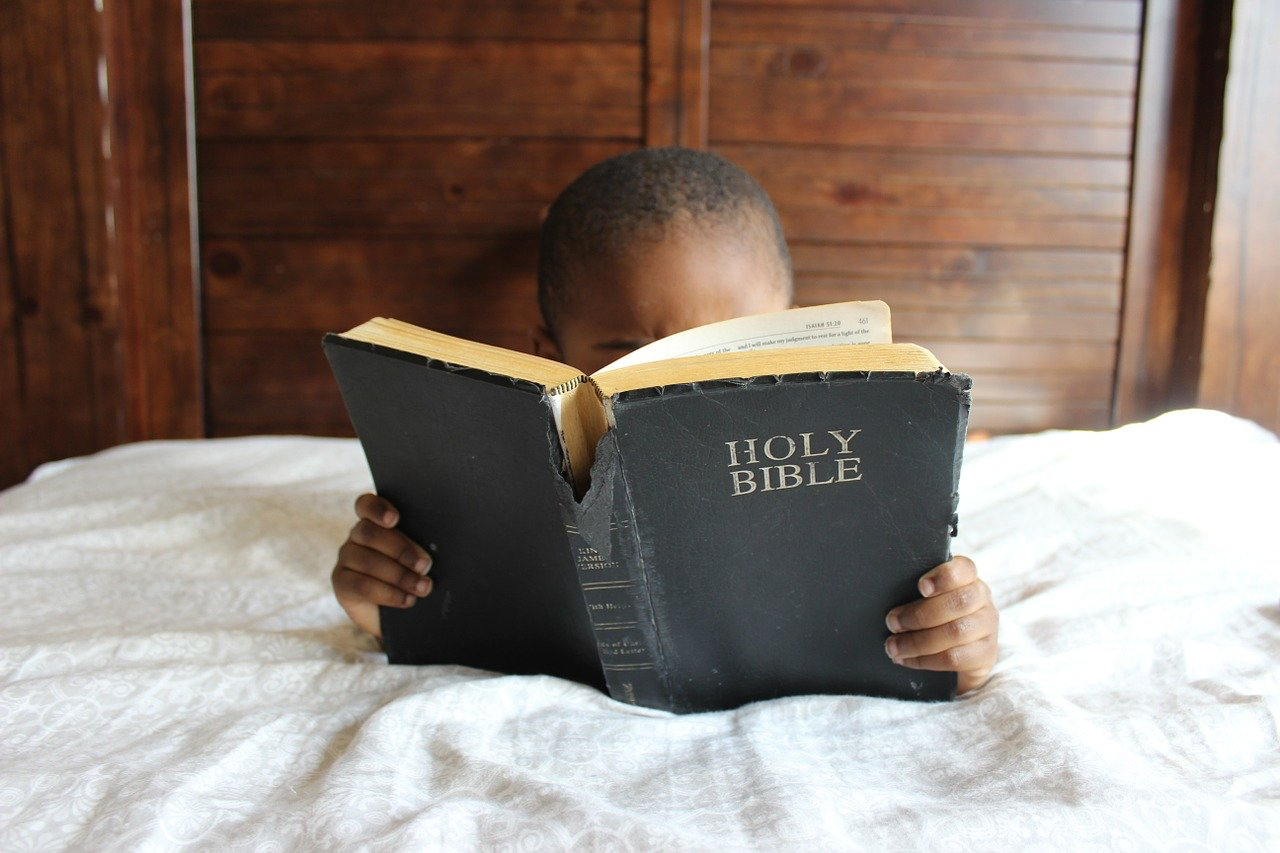目次
最短最速で起業から軌道にのせる方法
今回の起業東京.comでは、
起業家ならだれもが知りたい、
『起業から軌道にのるまでを最短最速にする方法』を紹介します。
いくらやる気に満ち溢れて起業するのでも、
しなくてよい苦労や、
無駄な時間は避けて通りたいものですよね。
軌道にスムーズにのせられれば、
あなたのやりた事の自由も広がるでしょう。
今回は、そんな理想の起業後のため、
具体的にどのように取り組むべきか、
わかりやすく方法をご紹介していきます。
早く、低コストで失敗する
起業のアイデアを考えついた時、まず考えるのは、投資がいくらかかるのかということでしょう。
もし大きな設備投資といった大金が必要になる場合、失敗したら存続も危ぶまれるほどだと思います。
会社が存続できたとしても、次の事業機会に恵まれたときにそこへ投資する余力がなくなってしまいます。
そこでおすすめなのは、事業をなるべく早い段階でテストを実施することです。
それも低コストでしなければなりません。
なぜならコストが多くかかってしまうとより多くのテストを実施できないからです。
無限に資本があるならテストにいくらコストがかかってもいいかもしれませんが、実際はそんなことはないでしょう。
だから低コストでできるテストを繰り返すことが大事になってくるのです。低コストなので、資金を圧迫することもないでしょう。
さらに、テストを多く実施することで成功への時間も短縮することができるようになります。
しかも、低コストでテストをするメリットは、大きくなる見込みのない事業を誤って掴んでしまったときにも簡単に方向転換することができます。
もし、コストをかけてテストもすることなく足を踏み入れてしまっていたら、簡単には引くに引けなくなってしまいます。
そういう意味でも出来るだけ低いコストでテストを実施することが重要なのです。
量と質の転換
ビジネスの世界では、アイデアがいいからといってすぐに目が出るとも限りません。
市場の魅力度、成熟度、成長率、競合の有無など、あらゆる不確定要素によって結果が大きく左右されます。
『千三つ』という言葉があるように、1000のアイデアのうち成功に結びつくアイデアは3つ(わずか0.3%)しかありません。
そんな厳しい世界で、1つや2つのアイデアを思いついただけで、すぐに起業に成功する確率は極めて低いです。
前述のテストに踏み切るまでにはアイデアの絞り込みが必要ですが、最初の段階ではブレーンストーミングを行って豊富なアイデアをどんどん出していくことが大事になってきます。
限定されたアイデアからは、凡庸なアイデアしか生まれません。
豊富なアイデアからは、優れたアイデアが生まれる確率が高くなります。
5分で考えつくことはライバルも5分で考えつく
今まで誰も過去に思いついたことのないアイデアをいきなり思いつくことは不可能に近いことです。
ほとんどの場合、過去に誰か別の人が思いついたアイデアと何か重なる部分が出てきます。
しかも、そのアイデアが事業化されてしまっていたりします。
重要なことは思いついたアイデアをいかに深掘りして考えられるかです。
思考が煮詰まるまで考え抜いて、さらにそこからもう一歩先に思考を進めることが大切です。
いかに早くやって失敗して、成功に近づけるか
リーンスタートアップという言葉が話題になりましたね。
リーンスタートアップではまず最低限のプロトタイプを製品を作るといいます。
そのプロトタイプへの顧客からの反応をもとに、事業アイデアや製品スペックの改良・軌道修正を図っていきます。
「レディ→ファイヤー→エイム」という言葉もあります。
英語で書くと、「ready→fire→aim」です。
日本語に直すと、、、「準備して→撃って→狙え」です。
普通なら準備して、狙って、撃つのかな、、とか思ってしまいますが、
狙ったしてもベストな着地をするか分かりませんので、まずは撃ってからそこからの反応をもとに狙っていく方が早く正解にたどり着けるのですね。
いかに早く失敗できるか、が成功の要諦になるようです。
PDCAフレームワークを振り回せ
早く低コストでテストをする上で、とても重要になるのが、PDCAサイクルです。
スペルにすると、「Plan→Do→Check→Act」で、
日本語に直すと、「計画→実行→評価→改善」です。
新しいアイデアを思いつき、それを計画に落として、テストし、さらに評価し、改善点を見出すという流れです。
重要なことは、改善点を見出した後すぐに次の計画を立てる(=仮説を立てる)ことです。
そうすることで、次の実行までのスピードが早まります。
このようにPlan→Do→Check→Act→Plan→Do→Check→Act→Plan→Do→Check→Actと、PDCAが螺旋構造のように連なり合わせながらテストの精度を上げていくことが成功への近道となります。
よく「PDCAサイクルを速く回せ」というのはここから来ています。
次のステージは、PDSE (Plan-Do-Study-Evolution)へ
PDCAの次のステージがあります。
それは「PDSE」と呼ばれています。
スペルにすると、「Plan→Do→Study→Evolution」で、
日本語に直すと、「計画→実行→学習→進化」です。
PDCAと違うところは、最後のStudyとEvolutionの部分ですね。
事業を改善しているとそれまでの考え方、慣習が邪魔になって、大きな壁にぶつかってしまうこともあると思います。
そんな時は、事業内容というより、事業構造や業界自体を変化させなければ問題解決にならないこともあるでしょう。
だから、仮説を立て、それを実行に移し、そこで失敗したことから学んで(Study)、ブレークスルーを起こして次元を一つ上に上げる(Evolution)ことが必要になってくるでしょう。
いかがでしたでしょうか。
なぜ、起業では低コストのテストを一刻も早く実行し、そこからの学びを「進化」に変えていかなければいけないというお話をさせていただきました。
あなたの起業の一助になれば幸いです。
参考文献:
MBA100の基本(グロービス著)
MBAビジネスプラン(グロービス経営大学院著)
MBA事業開発マネジメント(グロービス経営大学院著)