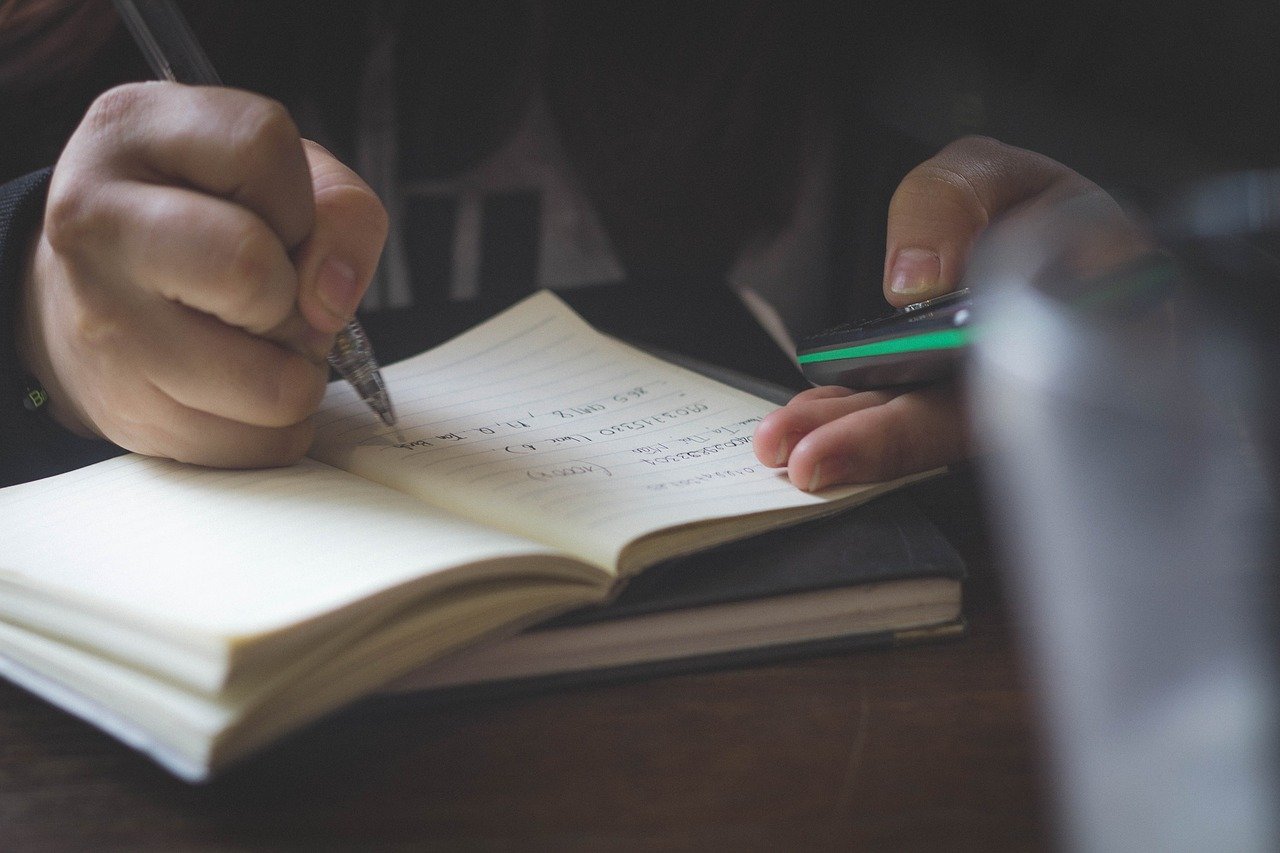目次
生のコンサル事例紹介!60過ぎてから動画編集を身につけた社長【動画あり】
続・生のコンサル事例紹介!起業家の失敗しない「人」の選び方【動画あり】
この記事では、弊社の代表取締役である
元ドクターシーラボ社長「池本克之」のコンサル事例の一部を紹介します。
起業するために重要な知識や考え方を、実際の経営相談から学べるチャンスです。
ぜひご覧になってみてくださいね。
特に起業する際、
ビジネスパートナーに適する人はどんな人か迷われている方
従業員を雇用しようと思うが、選考基準がわからない方
は、必見です!
今回のご相談は、採用に関する内容です。
ECサイトの店長を任せる人を探していて、ウェブテストを活用して選考を進め、5人が残りました。
その後、これまでの経歴や、詳しいテスト結果を参考に、「この2人のどちらかかな」という段階まで来ています。
(※EC:電子商取引。ネット通販のようなものだと思ってもらえればOKです)
●テストは優秀、通販の経験が浅い30代の応募者
●テストは平均、通販の経験豊富な50代の応募者
この2人だったら、一体どちらを採用すべきでしょうか?
以下、Youtubeで池本がお話しした内容を抜粋してお伝えします。
60過ぎてから動画編集を身につけた社長
●池本:
「技術を知らない」と言っても、
勉強すれば一通りできるよいうになります。
極端な話をすると、
例えばPhotoshopで画像をいじる技術。
30分ぐらい勉強すれば一応一通り使えます。
2〜3日勉強すると立派なものです。
例えば、動画の編集。
年齢でいうと60代くらいのそこそこの、
100人〜200人の会社の社長さんが
「これからはやっぱり動画の編集ぐらい
できないといけないだろう」
と思い立ったので、
1日動画編集の外部の講習会に行ったそうです。
講習会から帰ってきた社長は、社員に
「行ったら俺できるようになったよ」と。
すると社員は
「えぇ〜社長そんなこと興味あるんですか?」
と驚かれていたそうなんですね。
それに対して社長は、
「いや面白いじゃん」
「若い人らみんな勉強した方がいいよ」
「これぐらい出来ないとこれからダメだよ」
「AIの時代だよ」と。
動画とAIは関係ないので、
言ってることが噛み合ってないですが(笑)
という社長がいた話を、
若い担当の人から聞いたんです。
だから、そんなもんなんですよ。
技術の習得とは。
やる気があって「面白いな」と思ったら、
30代の人なんかは、
あっという間に技術を身に付けます。
それに対して50代の人は、
全員が全部がそうだとは言いませんが、
自分から主体的に動いて勉強していこう
という意識は一般的に、年齢と共に減退していきます。
ですから今までの経験に基づいて
「こうに違いない」という
固定概念が強い傾向にあります。
若い人は
「じゃあ新しいものを取り入れてもっと良くしましょう」
「変化していきましょうよ」という傾向が強く、
WEB診断の結果なんかも伺っている
と30代の方のほうがいいと思います。
で、選ぶ要素、最大の重視すべき要素は
「人間性」です。
私はこれを「スキル」と「モラル」
という言い方をしています。
「スキル」と「モラル」とは?
スキルは技術。
動画の編集とかPhotoshopとかのスキル。
これは勉強すればなんとかなる。
モラル・人間性の方は、勉強しても教えても
固定概念が強い人はどうにもなりません。
モラルを間違って採用してしまうと、採用で失敗する。
こうなると、教育では取り返せません。
いくら教えてもできない人は出来ません。
特に(スキルよりも)モラルの方。
だから必ず「モラル重視」で選択してください。
モラルを見極めるための方法として、
私は「100個の質問」というのをご紹介してます。
面接なので、大事なことは
「その人は受かろうと思ってきてる」
というところです。
応募者は、
「なんとかして受かって、
この会社で採用してもらえないかな・・」
と思って来てますから、
基本的にいいことを言います。
例えば、
「ネットでよく使うサービスはなんですか?」
という質問があった時。
本人は
(実はネットあんまり見ない…)
と思っていたとしても何か答えますよね。
「いやあんまりネット見ないんですよ」
と言ったら落ちるから。
「ああですこうです」って、
もう思いついたことワーっと言いますよ。
ということなので、
面接の上手い人には騙される可能性があるんですよ。
その面接上手な人も、
面接官を騙せない質問が1個あって。
それは
「第三者はあなたをどう見てますか?」
という質問です。
例えば、
「あなたはお友達からどんな人って言われることがありますか?」
と質問されると、
(友達…あいつか…飲みに行ったとき「お前はこうだよな」って言われるな)
と考えるわけです。
これって嘘つけないんですよ。
嘘がつきにくい質問なんです。
「大学からの友達でこんな奴がいまして、
その友人にはこんなことを言われます」
これって友人から見た目がそのまま出てる。
そういう質問は、
本人が脚色しにくい・盛れない質問です。
このような質問を駆使していただくといいと思います。
「再調達コスト」という考え方
●相談者:
給料についての質問なんですが・・
今回、若い人を採用したときに、
ECサイトの店長という仕事を任せるので、
すでにいる社員の給料を抜いてしまうことになるんです。
社員から反発が来るかもと思うのですが、
それは会社内で隠しておくべきなのでしょうか?
●池本:
これは極秘にはできないです。
社長が極秘にしたつもりでも、
入社して3ヶ月以内に社員全員知ってます。
給与振り込み(銀行の振込操作)は誰がやられてますか?
●相談者:
私ではなくて、スタッフがやっていますね。
●池本:
その人から漏れます。
隠さなければいけないとしたら、
これは人事制度が間違ってます。
やるべきことは二つ。
若い人は、今の先輩よりも
高い給料で採用したらいけないというのが一つ。
「それじゃあこの若い人が入ってきませんよ」
というんだったら、給与テーブルが間違ってます。
全員上げないといけない。
でないと、必ず辞める人が出ますよ。
給与低いということは、
会社・社長からの評価が低いということですから。
「入ってきたばかりの若い人よりも自分の評価が低いのか」
「やってらんないよ」と感じるでしょう。
「再調達コスト」という考え方があるんですけど。
例えばこれを、ある機械だとしましょう。
新品をもう一回買うとすると、
今だったらいくらするの?
というのが再調達コストです。
新品買ったらいくら?と。
人間も同じです。
例えば25歳で、
3年前に採用して給料25万円。
この人が辞めちゃったと。
同じような25歳の、
同じようなスキルを持っている人。
3年経験してるんですよ。
この人をもういっぺん採用するとしたら、
今いったい給料いくらじゃないと採用できないんだろう?
あるいは、
その採用をするためのコスト、いくらかかるんだろう?
これが再調達コストです。
この話からすると、
『再調達コスト=市場価格』なんですよね。
御社のような業界で働く、
25歳で経験3年の人の年収は、
もしかしたら27万円かもしれない。
当時、安く採用できていた頃よりも上がってますね。
それが相場です。
ということは、この人は何を考えるかというと
「うちの会社は相場よりも給料が低い。
なので相場並みの給料を出してくれる同業他社に移ろう」
と考えても不思議じゃないですね。
で、この人を失うと、
確かに27万円の給料でしか
次の人が入ってこないんですよ。
で、採用コストがかかるんですだったら、
辞める前の人に最初から27万円払った方がよくないですか?
それが今の再調達コストで、
適正な報酬レベルですよという話。
今の給与は、適性よりも低いんです
で、それが実は適性よりも
君ら低いんだ、ということを
新しい人を採用したことでバレちゃったという話です。
●相談者:
なるほど・・
ただ今回は、ECサイトの店長という
新しい責任ある立場で採用するので、
また別の給与体系を用意したんです。
基本給が最初から高い代わりに、
売上目標をきちんと達成してもらう必要があります。
なので、若い人を採用しても
給料が高いことには納得してもらえると思うんですが。
●池本:
なるほど。
だとするとそれは確かに給与体系が違うということなので、
この人の方が給料高いですということになるかもしれません。
けど、その場合は、今度は入社後の評価。
じゃあそうならなかった場合は社長どうなるんですか?と。
この人、1年経ってもさっぱり売れませんよと。
なのに給料高いまんまですか?
おかしくないですか?
となりますよ。
だったらやっぱり、評価制度を変えないとおかしいですよ。
新しい部署・新しい役職ができたんだから、
新しい評価制度を追加するんだと。
この役職・この部署の給与体系はこうですよ。
うまく行ったら上がっていく、
最初から高いでも1年経ってダメだったら下がる。
という新しい給与体系ができました。
これを伝えなければいけないです。
「いや社長、だったら僕がそれやりますよ」
という人もいるかもしれません。
「そっちやりたいです」と。
だって経験そんなにない人が入ってきてから勉強してやると
「だったら自分も一緒ですよ」と。
「経験ないけど会社のことはよく分かってます」
「商品のこともよく分かってる」
「スキルは勉強してそっちやりたいです」
という人がいたって不思議じゃないですよね。
そのためにも公表すべきです。
評価制度・人事制度は
会社からの一番のメッセージですから、
何をやったら評価される=給料が上がるか?
あるいは下がるか?
という一番わかりやすいメッセージです。
そのメッセージを隠して、
新しく入ってくる人にだけ約束して・・
ということにしてしまうと、
会社が何を考えているか分からないんですよ。
「社長、何を考えてるんですか?」
「なんであの人は給料高いんだ?」
で、憶測が飛び交いますから。
「あの人は、うまく行ったら給料維持で、
駄目だったら給料が下がるらしいよ」と。
公表すれば、
「あぁ、それだったまあしょうがないよね」
「ちゃんと1年後になったら査定があってダメだったら下がるんでしょ」
「大変な仕事だからそれは最初から給料高くて、1年経って凄いことになってるんだろう。給料が上がる」
「それはそうよね」
と。
ここを明確にしておかないと、
変な話というか・・
例えば
「22歳の若い女の人を採用しました」なんて言うと、
社長との関係者か?みたいな憶測が広がることがあります。
なのでそこはきっちり説明した方がいいですね。